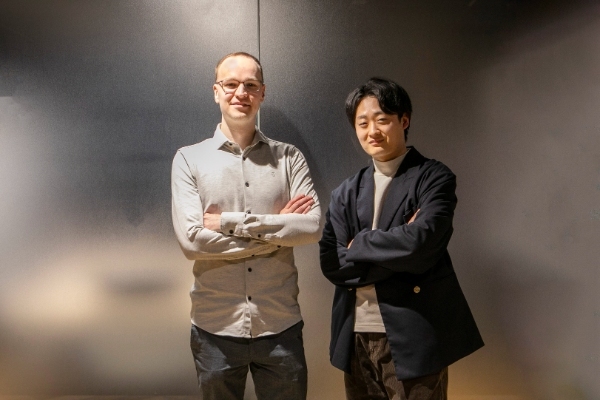写真右が開発フェローの金子敏幸
Photo by 新井 賢一
カメラが捉えた映像や画像を集約してAIが分析し、データを蓄積していくAI導入・運用プラットフォーム『OCTOps(オクトパス)』。
株式会社シーエーシー(以下、CAC)のR&D本部で開発され、これから製造業を中心にさまざまな業種・業務領域に普及させていく予定だ。
CAC版MLOpsとして開発されたこのプロダクトを普及させていくには、開発と営業の連携が不可欠といえる。
『OCTOps』のプロダクトオーナーとして全体のマネジメントと営業を担当する光高大介(写真左)と、開発を担当する金子敏幸(同右)の対談を通じて、『OCTOps』の開発秘話や今後の展望を読み解いていく。
大学卒業後にシステム開発関連企業に入社し、シリコンバレーでの勤務などを経て2014年2月に株式会社シーエーシーに入社。金融機関向けシステム開発等の企画に従事した後、2018年からR&D本部で製品の企画やプロジェクトマネジメントなどを担う。現在は『OCTOps』のプロダクトオーナーとして企画・営業をリードする。
>>CAC、製造業の現場などを効率化するAI導入・運用プラットフォーム「OCTOps」を提供開始
>>R&D本部サービスプロデューサーが語る最新のAI導入・実行プラットフォーム『OCTOps』とは
2000年に株式会社シーエーシーに入社後、金融システム部門に所属し銀行向けのシステム開発に従事。2008年以降は銀行・信託・証券などのSI事業のプロジェクトマネージャーやトラブルプロジェクトの立て直しを担当。2022年からR&D本部に籍を置き、複数のR&Dプロジェクトを推進。新技術の獲得とそれらを活用した開発をリードする。
>>命を守る『まもあい』が生まれるまでの開発秘話 魅力あるプロダクトに仕上げたチームマネジメント
――まず、おふたりの経歴と現在の業務内容について教えてください。
光高 私は2003年にシステム開発関連の会社に入りました。シリコンバレーでの勤務などを経て、2014年2月に中途採用でCACに入社しています。
CACではまず金融系のお客さまのシステムをリニューアルするプロジェクトに3年程度関わり、その後は金融系のお客様に対する、新しいサービスを立ち上げる部門で2年ほど活動しました。
次にデジタルソリューションビジネスユニットというDX系のサービスを扱う事業部に移り、そのなかのR&D部門(現在のR&D本部)に2018年にジョインして現在に至ります。
R&D本部ではプロダクトの企画やプロジェクトマネジメントに携わりつつ、どちらかというと営業的な立ち位置でお客さまと折衝しながら事業を拡大させることが私のミッションになります。

金子 私は2000年にCACに新卒で入社し、そこから20年近く、金融のお客さま向けのシステム開発を担当していました。
その後、2020年に金融ソリューション営業部に所属し、2022年にR&D本部に異動しました。現在は主に技術側でプロダクトの開発や、開発プロジェクトのマネジメントを担当しています。
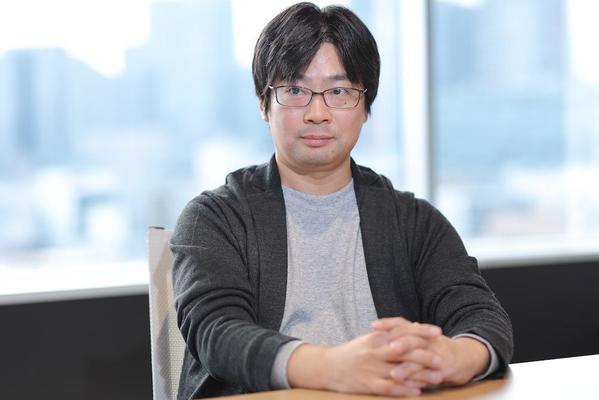
――おふたりが最初に接点を持ったのはいつ頃でしょうか。
光高 金子さんがR&D本部に来た当初は、それほど接点はなかったと思います。明確に関わり始めたのは『OCTOps』のプロジェクトが始まってからだと思います。
『OCTOps』は、最初は『MLOps※』という仮称で開発がスタートしました。金子さんは最初から『MLOps』に関わっていて、私は途中から関わり始めたので、そのタイミングからですね。
※MLOps(Machine Learning Operations)とは、機械学習モデルを開発から運用までの一連のプロセスを効率化し、自動化するための手法。
金子 光高さんももともと金融システム部門にいましたよね? その頃に一度だけ会ったことがあって、そのときに光高さんの存在を知りました。
光高 何のときでした?
金子 あるお客さまへの提案のときに、少しだけ絡みました。でも、そのときは顔を知ったぐらいで、R&D本部でもしばらくは別のプロジェクトだったので、やはり『OCTOps』の開発の中で頻繁にやり取りするようになった感じですね。
――当時の『MLOps』、現在の『OCTOps』を開発するきっかけを教えてください。
金子 『OCTOps』はAI実行・運用プラットフォームで、自社開発AIのメニューからエッジデバイスに適用するAIの選択、AI推論時のパラメータ調整、AI推論結果の映像による可視化、AIの再学習による継続的な精度向上などを遠隔操作で実現するプロダクトです。
開発したAIを現場に適用する際、AIとセットで、その現場向けの運用システムを作ることになりますが、このシステムはだいたい似たものになります。それならば同じようなものを毎回作るのではなく、プラットフォームを1つ作っておき、そこにAIを載せて動かすようにすれば、毎回、システムを開発するという非効率がなくなるのではないか、と思ったことが出発点ですね。
光高 私は『OCTOps』の機能が形になり始めた頃にジョインしました。『OCTOps』の機能がある程度そろってきた時期で、これをどういったお客さまに向けて展開していくのか、ある程度業界を絞って営業をしたほうがいいんじゃないかという議論がされている段階でした。
私はずっとAIをお客さまに導入するための営業をしていたので、その経験から、AIが導入される余地が大きい製造業に営業していくという方針を決めました。

――お互いについて、優れていると思う部分を教えてください。
金子 光高さんは開発に対する理解が深いことから言葉に説得力があり、お客さまのニーズを聞き出しつつ提案をうまく通してくれるという印象があります。
AIとはどういうものか、AIに何ができるのかという理解があるうえでお客さまと話をしているので、具体的なイメージを伝えながらニーズを引き出すことができていると思いますし、そこが非常に優れていると感じています。
光高 金子さんがR&D本部にジョインする前でも、スポット的なAIを利用したアプリケーションの開発ができるメンバーはいました。ただ、お客さまに恒常的に使ってもらえて、自分達が継続的にブラッシュアップしていくといった、本当の意味でのプロダクトを開発し、それを運用していくスタンスでプロジェクトを進めてくれるメンバーは育っていなかったと思います。
金子さんは金融系システムの大きな案件のプロジェクトマネージャーの経験があるので、チーム全体をまとめ、計画的に物事を進めていく能力があります。また、AIなどの新しい技術をどうやってプロダクトに取り込んでいけばいいかを考えることにも長けています。
私自身、営業の立場としてお客さまと話をする際には、AIにできることを踏み込んで話をしたいときもあるのですが、そこは少し抑えて、開発者である金子さんの意見を聞くようにしています。
あれもできます、これでもできますとお客さまにお伝えし、その後に機能を実装するのが難しいとなっては問題ですから、開発と営業でバランスを取りながら話をするようにしています。私やR&D本部がそのようにバランスのいい動き方ができるようになってきたのは、金子さんの力が非常に大きいですね。
――『OCTOps』の開発にあたって苦労した点を教えてください。
金子 AIはものによって処理の重さやエッジデバイスに必要なリソースが全く違います。『OCTOps』は複数のAIを1つのプラットフォーム上で動かし、なおかつ、それぞれのAIが異常な動作を起さないようにコントロールしなければなりません。
エッジデバイスというハードウェアもAIというソフトウェアも、予め固定されないなかで、うまく全体のバランスを取れるように作る部分に意外と手間がかかりました。

――開発にあたって、お互いにどのようなコミュニケーションを取りながら進めたのでしょうか。
光高 開発に関してはほぼすべて金子さんにお任せした感じです。これからお客さまへの展開が進み、実際に利用されるフェーズになっていったときに、こういう機能があったほうがいいという要望や意見は出てくるでしょう。そこは金子さんとコミュニケーションを取って『OCTOps』に反映させていきたいと思います。
金子 実際、『OCTOps』をお客さまに提案しているなかで、すでにいくつかのフィードバックをいただいているので、それを参考に機能のブラッシュアップを始めています。
光高 『OCTOps』は大きな構想として考えており、この先1、2年ではまだまだ完成形には至らないと思っています。製品の基盤も含めた全体の機能をどうブラッシュアップさせていくかについても、金子さんとすり合わせながらやっていかなければならないと思っています。

――ちなみに、なぜ『OCTOps』という名称なのでしょう?
金子 光高さんの発案です。なぜ『OCTOps』だったんですか?
光高 大阪に行ったときに、タコのぬいぐるみを子どもに買ったんですよ。それがヒントになって「タコもいいかな」と。
金子 そうだったんですね。今、初めて知りました(笑)。
光高 名称を決める時に、金子さんに相談しましたよね。「『OCTOps』ってどう思います?」って。
金子 「なぜタコなのだろう?」とは思いましたが、私自身は名称にこだわりはなかったので、異論はありませんでした。
光高 ロゴは2案あって、それも相談しました。実はそこだけは金子さんと意見が分かれました。私の意見を押し通すこともできたのですが、さすがにそれはやりたくないなと思いまして。
R&D本部のメンバー全体にアンケートを取ったり、西森(良太)社長や、今は新規事業開発本部でプロダクトオーナーを務めている定清奨さん、ジョイス・ファムさんといった元R&D本部のメンバーに意見をもらったりもしました。多数決では私が推していたものが優勢だったのですが、最終的にはもう一方のロゴに決めました。
金子さんもその一人ですが、私が信用できると思った人たちの意見がもう一方のロゴだったので「あ、こっちだな」と(笑)。そこで方向転換しました。
>>ITの力で日本経済のベースアップを ITプロ人材シェアリングサービス『WithGrow』に懸ける熱い思い
>>ジョイス・ファム インタビュー「AI技術を用いて医療・介護の課題解決 現場の想いを込めた『まもあい』が提供する価値」

――『OCTOps』の将来の展望について教えてください。
金子 多くのお客さまに使っていただくことが目下の目標です。
また、より広い業種や業務、工場だけではなく屋外の製造現場や建設現場など適用できるシーンをどんどん増やしていき、『OCTOps』を育てていきたいと思っています。
そのためには『OCTOps』というプラットフォームに乗せるAIの質が重視されます。AI開発はR&D本部としても高い優先度で研究開発、技術獲得を進めていかなければならないと思っています。
光高 ビジネスとしてはプラットフォーマーになっていくほうが有利だと思うので、プラットフォーマーに近い形でビジネス展開していきたいと考えています。
また、『OCTOps』は国内だけでなく海外でも使っていただけると思っているので、海外展開を目指していきたいですね。
実際、名古屋での「第7回 スマート工場EXPO」に参考出展した際にも「海外でも使えるんじゃない?」という話をいくつかの企業さまからいただきました。今後は、海外にもアピールする仕掛けを考え、動いていきたいと思っています。
――そのあたりも『OCTOps』という名前のイメージどおりですね。
光高 なるほど! そうやって手足を広げていく(展開する国を広げていく)。そこまでは考えていなかったですね(笑)。柔軟にいろいろなところに『OCTOps』を広げていきたいと思います。
金子 この『OCTOps』もそうですけど、今はAIなくしては考えられないような世の中になっています。
至るところでAIが動いていて、新たなAIが日々誕生している状態のなかで、CACとしてはAIの開発能力を備えたシステムインテグレーターであることが非常に大きな強みになっていると思います。
それをアピールする手段のひとつが『OCTOps』です。『OCTOps』を通じて我々のAI開発力が適用できる領域を広げていったり、世の中を便利にできるようなものを作っていったりできるようになればいいなと思っています。

>>CAC、製造業の現場などを効率化するAI導入・運用プラットフォーム「OCTOps」を提供開始
関連記事
・AIの力で養殖業界の変革を目指す『FairLenz』 開発におけるマネージャとメンバーのコミュニケーションの重要性
・「コンビをチームに」。生成AIプロダクトの開拓者たちが見据える夢
・技術と発想を掛け算 キーパーソンの対談から紐解くCAC流の新規事業開発