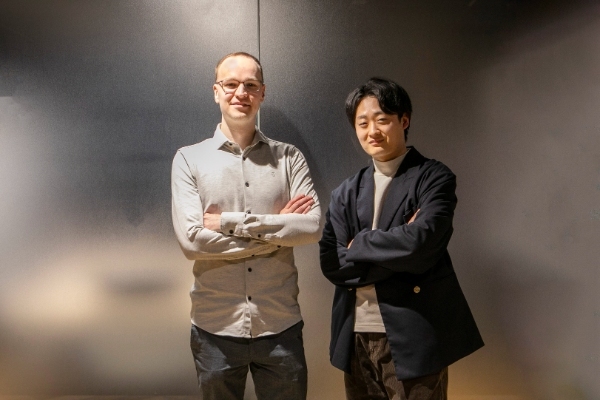医薬品製造に関連するITシステムを検証し、想定通りの動作を保証するCSV(Computerized System Validation:コンピュータ化システムバリデーション)は、医薬の品質保証、安定供給への貢献を通じ、安全・安心な医療を陰で支える仕組みの一つです(関連記事)。
今回は、株式会社シーエーシーで「CSV支援サービス」を担当する3人にインタビュー。製薬企業のシステム導入・更新に伴うCSVを外部専門家としてサポートする、業界内でもユニークな取り組みの具体的内容や実績について聞きました。
サービスプロデューサー
1996年シーエーシー入社。入社以来、医薬系・産業系部門のプログラム開発からプロジェクトマネージャー業務まで、多くのプロジェクトに従事。2021年、CSV対応クラウド環境の構築・運用サービスの立ち上げに携わり、CSV支援業務の一環として文書作成や検証作業を自ら実施し、プロジェクトを推進。
また、社内のCSVサービス担当者向けにGxPおよびCSV関連の教育研修を主導。
2015年までの約20年間、製薬企業向けコンサルティング会社にてシステム開発に従事。Part11制定当初よりCSVの実施に携わる。CROへの移籍とそこでのシステム部門長としてのCSV文書レビュー等を経て、2020年よりシーエーシーに在籍。
同業界における経験を活かし、GxP適用のクラウド環境構築・運用サービスの立ち上げや、CSV支援サービスに携わり、現在に至る。
大学卒業後、IT企業にてシステム開発・運用・営業を経験し、2017年に株式会社シーエーシーへ入社。現在は、製薬企業向け営業を担当。これまでの経験を活かし、CSV支援サービスをはじめとするGxP関連サービスの営業に従事。
顧客の課題解決に向けて、提案活動を行っている。
保存を紙からデジタルへ。業務効率化が求めるCSV対応

−皆さんの担当業務を、まず簡単にお聞かせください。
塩崎:私は、製薬企業のシステム構築にあたって規制対応をサポートする事業である「CSV支援サービス」の主担当を、2023年の開始以来務めています。
小寺:私はCSV支援サービスの企画段階から関わり、現在は実務とプロモーションを担当しています。この3人の中で社歴は最も短いですが、製薬業界向けのシステム開発経験は長く、20代の頃からずっとこの分野に携わっています。
清水:私は、CSV支援を含む製薬業界向けITサービスの営業担当です。もともとは別の業界でITエンジニアをしていましたが、開発に携わった医療系サービスの営業も担うようになり、8年前にCACに入社してからは、ユーザーである製薬企業との窓口役を務めています。
− CSVという仕組みに、あまりなじみがない人も多いと思います。外部のパートナーによる支援がなぜ求められているのか、背景を解説いただけますか。
清水:CSVは、システムのユーザーである製薬企業が導入や更新にあたって、規制要件を満たすための活動の一つです。そのため、基本的にはユーザー主体で行われています。
もっとも、安全性・信頼性を重視する製薬業界では、安定稼働している生産設備をそのまま維持する傾向が強く、付随するITシステムの更新サイクルも比較的長くなっています。システムの更新に際し「CSVは工場を建てたとき実施したのみで、当時担当した社員は誰もいない」というケースも珍しくなく、関連するノウハウが“ロストテクノロジー”になりやすい事情があります。
これがCSVにサポートを求められる大きな理由で、同種のサービスがあまりないこともあり、多くのお問い合わせをいただいている状況です。
小寺: ITシステムのベンダーが、納入する自社製品についてCSV対応を支援するケースは多いのですが、このとき一般的なのは、標準機能をそのまま使う前提で準備されたフォーマットを埋めていく方式です。そのためユーザー独自の業務手順や、他システムと絡めたシナリオなど、応用的な使い方をするとなると、ユーザー自身でCSV対応について理解して判断すべき事項が一気に増え、時間もかかるようになります。
加えて規制当局によるCSVのガイドラインは、具体的に何をすればクリアしたことになるか詳細を示していません。これはつまり、ユーザーが根拠を持って対応内容を自ら説明できることを重視しているということです。
そうした背景から、ユーザーが深く理解し、きちんと納得できるような対応方法を一緒になって考えられるパートナーが求められているように思います。

塩崎:医薬に対する厳しい品質保証体制の一環であるCSVは、生産設備の制御システムのように薬の品質を直接左右する部分だけでなく、製造記録やマニュアル類を保存する文書管理システムでも対応が求められます。
「文書を紙で残す」という、最もシンプルな管理方法を続けてきた製薬企業でも、検索性の向上などで業務効率を高めていく必要から、完全電子化に踏み切る例が増えつつあります。ここで必須となるシステムの新規導入に伴い、CSVの課題に直面した方々からのお問い合わせが、特に増えている状況です。
対応の“範囲と深さ”を説明可能にする

−ユーザーが主体のCSVを支援する活動とは、具体的にどのようなものですか。
小寺:先ほど触れたとおり、CSVは規制要件を満たすために何をどこまでやるのか、ユーザー側で判断する幅が広いのが特徴です。そのため解釈次第では、あれもこれも“かわす”ようにして対応範囲を最小化することも、逆にコスト度外視で徹底検証することも考えられますが、現実的にはいずれも極端で、お勧めできない方法です。
そこで私たちは、昨今一般的となりつつある「リスクベース」のアプローチ、つまり「この部分で問題が生じたとき、薬の品質に影響を及ぼす可能性がどの程度あるか」を検討していき、実際の対応方法を見極めていくお手伝いをしています。
塩崎:例えば、非常に多機能なパッケージシステムを導入する際も、CSVとして行う動作の検証は、ユーザーが実際に使う機能をカバーできていれば十分なことが多いです。
こうした対応の「範囲」「深さ」を検討、提案し、もし当局から問い合わせがあったとしても「なぜそうしたか」をきちんと説明できる状態にするのが、私たちのサポートの大きなミッションだと考えています。
また、検証の手順から結果までを全て文書で残す必要があるので、それらの作成の実作業についても手を動かしてご協力しています。
−システムのベンダーによるサポートで足りないとき、それを補うケースが多いのでしょうか。
清水:確かに、導入予定のシステムのベンダーがCSV対応のフォーマットを提供しているケースでは、当初ご検討いただいた私たちのサポートがなくても対応可能という結論になることもゼロではありません。
一方、提供されたフォーマットがお手元にあっても「専門外のITに関する大量のドキュメントの理解に不安がある」「内容に過不足ないのか主体的に判断して承認したい」といった理由から、私たちのアドバイザリーや実務支援を求められることもよくあります。「第三者視点からの解説者」「ベンダーとの対話を取り持つ橋渡し」といった役割ですね。
CSVから手順書改訂まで一貫支援の例も

−実際にCSVを支援した事例についても伺えますか。
小寺:私たちの実務的な役割や守備範囲をイメージしやすいものとして、ある製薬企業の文書電子化プロジェクトでCSVを支援したケースが挙げられます。
ご支援先である、医薬品の安全性に関する非臨床試験を扱う部門は、国が定めたルール(GLP省令)に基づいて標準操作手順書(SOP)や試験の計画書、報告書などの文書を適切に保存、管理することが求められる中、従来は紙で保存していました。
それらを、スムーズな情報共有や、適切な権限に基づく操作、また文書改訂に伴う履歴の保持や、電子署名による承認プロセスを確立するため電子保存に切り替えることとなり、「全社導入している一般的な文書管理システムを使いたいのでCSVを相談したい」とのご依頼をいただきました。
ご契約後、私たちも入ってお客様の要件と当該システムの調査を進めた結果、GLP業務への適用が仕様上困難なことが判明しました。ただ幸い、このお客様の一部の部署で使用中の別の文書管理システムであれば対応可能と分かり、対象をそちらのシステムに切り替え、あらためてできること・できないことの洗い出し(Fit & Gap分析)から、システムベンダーと共同でのユーザー要件に沿ったシステム構成設定のご提案、CSVのための文書ドラフト作成までお手伝いしました。
ご担当者様は、通常業務と並行でかなり多忙な状況でしたが、チャットなどで密にやりとりを交わしながら進め、ご依頼から約1年で無事リリースに至りました。
塩崎:この会社では、GLPのドキュメントが紙から電子になることで業務手順が変わり、SOPの改訂や一部の新規作成が必要となったのですが、ここでも私たちのご提案をもとに、スムーズな最終化や承認プロセスが実現したと聞いています。
製薬企業の文書管理では、GLPも含めて「GxP」と総称される分野別の基準があり、それぞれ国がルールを定めています。今回のケースでは、紙からの移行に伴うCSVとSOP改訂をまずGLPでクリアできたことから、このお客様の別部署にまたがるGxP全般の電子化も準備が進んでおり、引き続き私たちがご支援しているところです。
SOP(Standard Operating Procedure): 標準業務手順書
GLP(Good Laboratory Practice): 優良試験所規範
GxP(Good x Practice): 優良規範の総称、xは製薬における様々な段階に応じた英単語が入る
高い質の医療を持続させる一助に

−幅広く頼りになるパートナーという印象ですね。最後に今後の抱負をお聞かせください。
塩崎:国民皆保険制度のもと高齢化が進み、多くの薬が必要とされていることもあり、現在国内で処方されている薬の大半はジェネリック薬で、薬価の引き下げ傾向も続いています。こうした流れを受け、効率化につながるシステム導入で業務を変革し、体質強化を図ろうという動きが、中堅・中小の製薬企業でも目立ってきたように感じます。
そのときCSVが取り組みの壁とならないよう、引き続き私たちがしっかりサポートしていくことが、ひいては高い医療の質を持続させる一助にもなるのではないかと考えています。
小寺: CSVは薬の品質に今日明日すぐ影響するというよりは、常に確かな品質で作られていることを保証し、安定して作り続けるための仕組みです。そこで私たちもシステム導入・更新を終えるまででよしとせず、その後のスムーズな運用まで見据えたサポートで貢献していくつもりです。
清水:従来の低分子医薬品と製法が異なるバイオ医薬品では近年、化学メーカーが開発製造受託機関(CDMO)として参入する例が相次ぐ中、元が製薬ではないためにCSVや品質保証の知見が少ないケースがあり、システムのCSVについてお問い合わせをいただくこともあります。今後も、新たな試みの入り口で後押しができたら素晴らしいですね。
−とても興味深いお話でした。今回はありがとうございました。