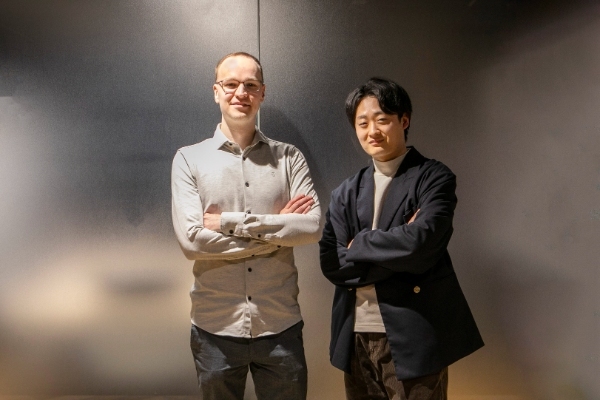CACグループでは2023年からグループ会社を横断した「女性役職者ワーキンググループ」という活動を行っています。その活動の目的は「意思決定層に求められる視座の獲得」。具体的には、
- 経営戦略と自部門の役割を結びつける視点
- 部門横断の課題発見・解決力
- 多様な人材の育成、活用のマネジメント視点
を参加メンバー各々が獲得していくことを目指します。
また、活動を通じて「女性役職者同士のネットワーク形成」も重要な目的としています。ライフイベントの影響を受けやすい女性だからこそ、仕事やプライベートを含めた悩みを気軽に相談しあえる関係性を築くことを意識しています。
名称だけを見ると ”女性だけの取り組み” と誤解されそうですが、実際は高い視座、広い視野を持つための場。グループ全体の未来を担うリーダーの成長を育む場となっています。
女性役職者ワーキンググループの背景
現在、CACグループでは女性従業員比率が30%を超えている一方、女性役職者比率は17.3%(2023年時点)にとどまっており、登用の不均衡が課題とされています。本ワーキンググループは、その状況を改善するために立ち上げられたポジティブ・アクションであり、構造的な差を是正するための積極的な取り組みです。女性役職者層の拡充は、将来的な女性役員候補層の育成にもつながる重要なステップであり、中長期的な後継者育成の一環として、継続的に実施されています。そして何より、ワーキンググループへの参加は参加者自身の視座や視野を広げる機会となり、議論を通じて生まれる提言や施策が男女関係なく全社の課題解決にも波及しています。ポジティブ・アクション:特定の属性において生じている構造的な差を解消するために、一時的かつ積極的に講じる取り組み
参加メンバーは第1回は20名、第2回は19名、そして2025年5月23日にキックオフされた第3回は CAC Holdings 、シーエーシー、アークシステムズの3社から29名が参加しました。このキックオフイベントでCAC Holdings代表取締役社長 西森良太が講話していますが、その中で西森は、多様性に対する自身の過去への反省と今の想い、リーダー候補であるメンバーへの期待とグループとしての決意をメッセージにしています。
Innovation Hubはイノベーションをテーマにしたメディアがですが、西森のメッセージの中には多様性とイノベーションの強い結びつきが述べられています。西森の言葉を通じて、CACグループの多様性に対する考え方とアクション、そしてイノベーションについて知ってもらいたいと思います。
若手だった頃を振り返って
私がCACに入社したのは1994年ですが、若手だった頃を振り返ると、自分自身の中に、言葉にはしてこなかったものの、男性としての立場や意識にこだわる気持ちがあったように思います。女性の上司、特にプロジェクトマネージャーに対して、無意識のうちに反発心を抱いていたこともありました。今振り返ってみると、これは性別に起因するものというより、当時の職場文化、そして私自身の若さ・未熟さに起因するものだったと思います。
一方で、女性社員の中にも、男性社員に対する競争意識やライバル心を感じる場面があったように記憶しています。それが一般的な傾向だったかどうかはわかりませんが、私自身はそのような空気を感じ取っていました。
それと、入社してから数年間、私の身近に女性の役職者の姿はほとんど見られませんでした。会社全体の動きを把握していたわけではありませんが、自分の記憶をたどっても、名前が思い浮かぶような女性管理職がいなかったことは確かです。私自身も、そして会社や社会も、当時はそういった偏った状況を問題と捉える意識すらなく、当たり前のように受け入れていたというのが正直なところだと思います。
社会の価値観の変化
当時の社会では、「男勝り」「姉御肌」「寿退社」など、今ではあまり使われない言葉が普通に使われていました。これらの表現には性別による役割への固定観念が色濃く反映されており、今では不適切とされることも多いでしょう。「イクメン」という言葉も一時期話題になりましたが、こちらも使われなくなっていると思います。今では男性が育児をするのは特別なことではなく、ごく自然なことです。
このように、時代とともに価値観や言葉も変わっています。私自身も、使う言葉には気を付けていますし、読んだり聞いたりする言葉一つひとつに社会の意識の変化が表れていることを実感しています。
意識を変えるきっかけと私自身の学び
私の意識が大きく変わる前にこういう出来事がありました。重要なプロジェクトのリーダーに、ある女性社員をアサインしようとした時のことです。彼女は、そのプロジェクトをリードすることに自信がないという理由で、アサインを断りました。その出来事が、私の中に「女性はこういったオファーを受けないのではないか」という先入観を生み、その後の重要なアサインの際に女性の登用について、一瞬考えてしまうようになったというのは事実です。
一方で、女性の登用について「自分の考え方をアップデートしなければならない」と強く思うようにもなりました。そのきっかけになったのがガバナンスサーベイという年次調査です。銀行や信託銀行が提供するこのサーベイは、自社のガバナンス状況やジェンダーバランスなどを客観的に評価し、数値やコメントとして可視化してくれます。
このサーベイで、私たちのグループが他国と比べてどれくらい遅れているか、初めて明確に認識しました。たとえばフランスでは取締役の約45%が女性であり、アメリカでもS&P 500企業の多くが女性比率の向上に努めています。それに対して、日本、そして私たちのグループはまだまだ追いついていません。この現実を知ったとき、強い衝撃と危機感を覚えました。
また女性役職者ワーキンググループの活動報告を聞いたり、メンバーと話ししたりすることで、「アンコンシャスバイアス」「オールド・ボーイズ・ネットワーク」「インポスター症候群」「ガラスの天井」といった概念を現実感を持って理解したことも大きな転機になりました。これまで漠然と感じていた違和感や体験に名前がつくことで、自分の中にあった無意識の偏見を、言葉として客観的に認識できるようになった。そのことで、思考と行動の修正ができるようになりました。
オールド・ボーイズ・ネットワーク:企業内で、男性中心に築かれてきた部署や役職を超えた非公式な人脈が、仕事や昇進、人事などに偏って影響を与えること。
インポスター症候群:成功していても自分の実力を信じられず、周囲をだましているように感じる心理状態。自己評価が低く不安を抱えやすい。
ガラスの天井:女性や少数派が昇進や活躍を望んでも、見えない障壁によって上位職に就けない状況を指す言葉。差別や偏見が要因。
加えて、最近の研究では「性差」よりも「個人差」の方がビジネスにおいて重要であるという指摘があります。これは、性別に関する議論を超えて、一人ひとりの特性や能力を尊重するべきだという考え方です。私にとっては、CACグループが進むべき方向を示す、まさに目から鱗が落ちるような納得感のある考え方でした。
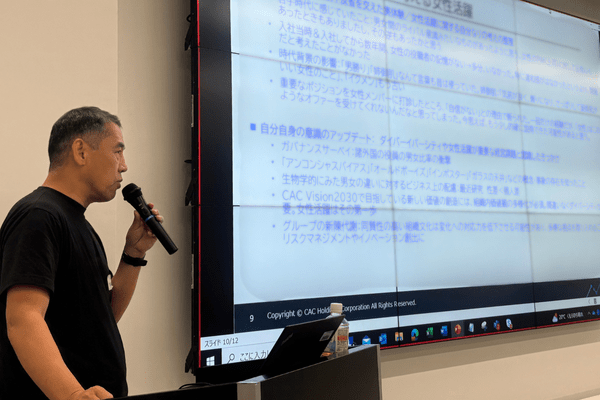
多様性(ダイバーシティ)が生むイノベーション
CAC Vision 2030「テクノロジーとアイデアで社会にポジティブなインパクトを与える企業グループへ」を実現するためには、価値観の多様化が不可欠です。異なる視点や経験を持つ人たちが集まることで、新しい発想や創造的な解決策が生まれるからです。
2023年にCACに新規事業開発本部を組織しました。私は、そこで提案される新規事業アイデアの実現可能性、収益性、成長性を見極めると同時にアドバイスする立場でもあったのですが、メンバーが出すアイデアの幅広さには驚かされました。男女や世代、バックグラウンドが異なることで生まれる視点や経験の違いは、アイデアの良さだけでなく、事業をドライブする力を持っていると実感させられました。
同質性が高い組織は、変化への対応力が低くなると言われています。一方、多様な意見が飛び交う環境は変化やストレスに強く、そして大小さまざまなイノベーションも生まれやすくなります。これは単なる理論ではありません。私たちが日々の業務で感じ取っている現実だと思います。
女性がリーダー、役職者として活躍することは、今のCACグループの多様性を高めます。女性役職者比率などのKPIはただ数値目標として置いている訳ではなく、それを達成するためのアクションが組織としての競争力を高めるのです。
経営としての責任と改革への決意
人事制度面では、結婚や出産などライフイベントに対応した支援施策や、男女で差がない評価制度などが整備されつつあります。しかし、制度が整っているだけでは不十分です。実際に女性が昇進や抜擢の機会を前向きに受け止め、自信を持って挑戦していくことが不可欠です。
タフなアサインメントや困難なプロジェクトに向き合うことは、個人の成長につながります。それを避けるのではなく、自ら手を挙げて挑戦してほしいと強く思います。社外から優秀な女性を採用することも可能ですが、社内で育てていく方がはるかに意義が大きいと私は考えています。
女性役職者が増えるには、女性役職者の候補である皆さんの、成長に対する意志が鍵を握ります。これは女性男性同じですが、社員一人ひとりがもっとスキルや能力を磨いていく必要がありますし、リーダー、役職に対して積極的に手を挙げて欲しいと考えます。昇進のチャンスは、待つものではなく、自ら掴みに行くものです。
女性役職者ワーキンググループへの期待とお願い
ワーキンググループの皆さんには、特に2つの点を期待しています。
1つは、この機会を成長の場として積極的に活用してもらいたいということです。自分を磨き、さらに上のステージを目指してください。皆さんの成長が、女性役職者比率を高めるための原動力になります。
もう1つは、後輩社員に対して、自らの姿をロールモデルとして示し、リーダーや役職、より大きなプロジェクトや役割に挑戦する姿勢を見せてください。ここに集まっている皆さんは既にリーダーや役職者、もしくはそれに近いという方ですが、皆さんの周りには、次に続くべき人材が必ずいます。次に続くその人たちに声をかけ、皆さんが勇気を与える側になって欲しいと期待しています。
まとめに変えて
私は、スキルや能力に応じて女性役職者が登用され、さらにその先、真に多様性が実現されたCACグループを自分の目で見たいと思っています。多様な価値観を持つ人々が共に働き、新たなイノベーションを生み出し、組織全体が成長していく未来。それは決して夢物語ではなく、私たち一人ひとりの行動によって現実になると信じています。
経営サイドも女性役職者の登用、多様性のある会社作りには全力で取り組んでいきます。皆さん一人ひとりが主体的に関わり、共に未来をつくる仲間となってくれることを、心より願っています。
(上記文書は、CACグループ「女性役職者ワーキンググループ」キックオフでの西森の講話を抜粋編集したものです)