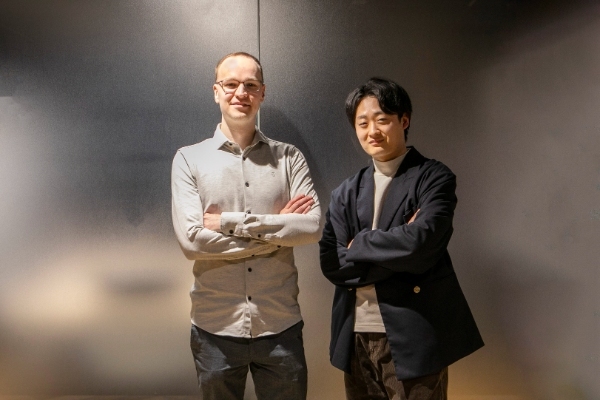研究開発を担うR&D部門のエンジニアの素顔を映す企画「エンジニアのヨコガオ」。今回は、2020年入社の高橋滉一が登場します。将棋仕込みの先読み力と、忖度のないストレートな提案力こそ、彼の真骨頂。その人物像を紐解きます。
高等専門学校で情報工学を専攻。卒業後、2020年に株式会社シーエーシーに入社。R&D本部に配属され、現在はシステム開発に従事。主に、生成AIを始めとする先端技術を取り入れた、運用業務自動化システムの設計・開発を担当している。
大切なのは、“どこで働くか”ではなく、“どう働くか”

――CACではリモートワークが定着するなか、今日は久しぶりの出社だそうですね。
はい、2週間ぶりに靴を履きました(笑)。在宅勤務中は、ちょっと外出する程度ならサンダルで済ませてしまうので、久しぶりに足元からスイッチが入った気がします。
とはいえ、リモートワークにも一長一短があります。特に最近は、むしろ業務を進めるうえでの“やりづらさ”を感じる場面が増えていたように思います。
――どういうことでしょうか?
生成AIの進化が目覚ましく、業務の進め方が急速に変わり始めているんです。1年前なら1週間かかっていた作業が、今では1日で終わることも珍しくありません。つい3日前にも、Anthropic社が『Claude』シリーズの最新モデルをリリース(*1) したのでさっそく試してみたら、作業スピードが従来の1.5倍ほどに。正直、想像以上でした。
ただ、AIツールの扱い方には個人差があり、リモート環境ではメンバーの習熟度や作業ペースが見えにくい。そのため、チーム全体としての適正な工数を見積もりづらくなっているんです。私のチームでは、来月から週2日の出社に切り替えることにしました。まずは対面で、AIとの向き合い方も含めて感覚をすり合わせる必要があると考えています。
*1:2023年3月に初版がリリースされた『Claude』の最新版が25年5月に発表された。最新シリーズ中の『Claude Opus 4』は、世界最高クラスのコーディング能力で、複雑な推論や文脈理解力で自律的にタスクを遂行。『Claude Sonnet 4』は、高いコーディング能力と効率性を備えたモデル。
――そうした視点は、どんなバッググラウンドで育まれたのでしょう?
高専で7年間、情報工学を学びました。1年生からプログラミングを始めて夢中になり、授業外でも仲間と一緒にアプリを開発したり、趣味でコードを書いたり。周囲に同じ志を持つ仲間も多く、居心地のいい環境でした。
卒業研究では、中医学の診断支援システムの開発に取り組みました。経験や勘に頼りがちな医師の診断を、システムでサポートする試みです。私にとってはそれが初めてのクラウド開発でもあり、新しい技術に触れながら形にしていくプロセスが楽しかったです。
――CACとの出会いは、どんな経緯だったのでしょう?
学生時代に参加したCACのインターンがきっかけでした。1カ月間、感情認識AIを活用したアプリの開発に取り組む内容だったのですが、私は元々、興味のあることはとことん深堀りするタイプで。与えられた課題を早めに終わらせたあとも、自分なりにさらに発展させていきました。
たとえば、学校の授業中の生徒の表情がどう変化するかをAIで分析し、「なぜその表情になったのか?」という要因に着目するアプローチを試してみたり。その試みはCACとの共同研究にもつながり、もともと進めていた中医学の研究よりも論文にしやすかったこともあって、最終的にはこちらを卒業研究のテーマに選びました。
インターンや研究を通じて、自分の考えやスキルをある程度は伝えられていたと思います。その縁もありCACに入社しました。CACのフラットな社風や、ユーモアのある人が多い職場環境は気に入っています。
自分にとって大事なのは、“どこで働くか”ではなく、“どう働くか”。自らの裁量を持ってプロジェクトを進められるCACのなかで、自分らしく働きながら力を発揮していくほうが、きっと楽しい人生になるだろうなと思ったんです。
将棋で培った先読み力で、ユーザー視点を突き詰める

――入社後、実際に働いてみていかがですか?
年功序列ではなく、提案の中身をきちんと見て判断してもらえる。その風通しのいい環境が気に入っています。
実際、私が所属しているR&D本部は、部門長のもとにメンバーがフラットに並ぶような組織体制です。その分、「こういうアプリ作って」といったアイデアや相談が、部門長から直接飛んでくることもよくあります。
そんなとき、自分のなかで納得できないことがあれば、私はその旨をはっきり伝えます。ある案件では、部門長の方針に納得できず、何度も意見をぶつけ合う場面もありましたが、粘り強く考えを伝え続けるうちに、「じゃあ一度まとめてみて」と言われ、提案資料を作成。その結果、「確かにこれはいいね」と評価され、採用されました。いまはそのシステム開発のプロジェクトリーダーを任されています。
――現在はどのようなプロジェクトに携わっているのですか?
AIを活用した、システム運用業務の自動化に取り組んでいます。イメージとしては、事務作業のような現場のルーチン業務を、最新の生成AIを使って自動化していくようなプロジェクトです。
――ズバッとモノを言うタイプなんですね。発言が裏目に出たような経験は…?
幸い、上司は懐の深い方が多いので、そこは大丈夫ですが、もしかするとちょっと扱いづらいと思われているかも……(苦笑)。でも、自分に嘘をついて人間関係を築くのが苦手なので、たとえ上司に嫌われたとしても、後悔はしないと思います。本音を言わずに場の空気を優先していたら、そのせいでシステムの質が下がるかもしれない。それこそ本末転倒ですから。
――同僚のエンジニアの方々も、率直に意見を伝えるタイプが多いですか?
いえ、どちらかというと、上下関係を大切にしながら、誠実に業務に取り組む人が多いと感じています。
ただ、AIを活用したシステム開発が進むこれからの時代は、「ユーザーがどういう環境で、どんな気持ちでそのシステムを使うのか」を想像する力が、より求められるはずです。エンジニアとしての技術力や忠実な姿勢だけでなく、「使う人の視点にどこまで立てるか」が、さらに重要になってくると思います。
――高橋さんの場合、そうした“ユーザー視点”をどのようにして身につけたのですか?
子どもの頃から祖父の影響で将棋を指していたのですが、その感覚が今の仕事に生きている気がします。将棋は、自分がこう指せば相手はこう来る、すると盤面はこう変わって、相手の持ち駒はこうだから、次はこう指す……といったように、何手も先を読み続けるゲームです。自分のアクションの先に何が起こるかを、常に想像し続ける必要があります。

システム開発も、それに近いところがあって、たとえばある機能をつくるとき、その機能を使うユーザーはどんな立場で、どれくらいの知識があって、どんな環境で使うのかを想像します。消極的な気持ちで使う人なら、ログインのひと手間さえ面倒に感じるかもしれないし、逆に慣れている人なら、それくらいは当たり前に受け入れてくれるかもしれない。
使う人の状況を思い描きながら、先の先を読んで緻密に設計していく。その感覚が、将棋で先を読む作業とどこか重なるんです。
AI時代でも絶対に譲れないもの

――ちなみにオフの時間の過ごし方は、ゲーム中心だそうですね。
ゲームとYouTubeと睡眠でほぼ完結しています(笑)。学生時代はオンラインで友達とパーティーを組んでゲーム内のイベントに出たりもしていましたが、最近は『Path of Exile』というハクスラ(ハック&スラッシュ)系のゲームをひとりで黙々とやっています。実は昨年、友人関係を一度リセットして、今は仕事以外の人間関係は“ゼロ”なんです……。
――友人関係をリセットとは、思い切りましたね。人付き合いは苦手な方ですか?
むしろ逆で、人と話すのは好きです。ただ、友達の優先順位が高すぎて、「そろそろ寝ようかな、でも友達がオンラインになるかも……」と考えてしまうのが、地味にストレスで。好きだからこそ、振り回されてしまう感じです。
悩んだ末に、「一回リセットしてみよう」と思ってスパッと整理したら、思いのほか快適で。とはいえ、何年後かに「やっぱり持つべきものは友達だよな~」ってしみじみ言っている可能性もありそうです。
――高橋さんの思い描く「未来」は、どんな世界ですか?
あまり明るい未来が思い描けなくて……。というのも、今の世の中は、本来見なくてよかった世界もインターネットによって簡単に見えてしまいます。見えないものは見えないままの方が、不必要に悩んだり、情報に振り回されずに済んだかもしれません。

もしかしたら、人間の進化において、インターネットは十分に扱いきれていない技術なんじゃないかと考えるときもあります。希望があるとすれば、インターネットと人との関係性がうまく変化して、今より良い関係になっている未来が来ることでしょうか。
――最後に、高橋さんが思い描く「エンジニアのこれから」とは?
生成AIが広く使われるようになって、特に画像生成の分野では、クリエイターの仕事が置き換えられる場面も出てきています。ただ、SIerやプログラミングの領域は少し様相が異なります。そこではまず、「作りたいシステム」があり、プログラミングはそれを実現するための手段にすぎません。AIが自動化できるのも、主にその“手段”の部分です。
これからのエンジニアに必要なのは、その手段を活用し、「何を、どう形にするのか」を設計する力だと思います。目的や利用シーン、求められる機能を深く理解していなければ、本当に価値のあるUIやシステムは生まれません。そうした構想力を持つ人が、これからの時代に求められるエンジニアだと思います。
私自身、プログラミングをやりたくてこの仕事をしているわけではありません。良いものを作り、世の中を便利にすること。その思いは、これからも変わらないと思います。
*
発言の前後を踏まえず、彼の“言葉”だけを切り取ってしまうと、高橋さんを見誤ってしまいます。尖った部分がフォーカスされがちなキャラクターの奥には、人が好きで、世の中を良くしたいという思いが脈々と流れているのを感じました。

▽技術者が気になる技術
特に関心があるのは人体工学、なかでも脳の解明です。脳のメカニズムが明らかになるかどうかで、AIの今後の進化は大きく変わるはず。AIの基盤となるディープラーニングも人間の脳の仕組みを模した技術ですから。
最近では、脳波から思考を映像化する技術も登場していますが、まだまだ課題が多い印象です。脳の仕組みの理解が進めば、こうしたデジタル技術にも新たな可能性が広がると期待しています。