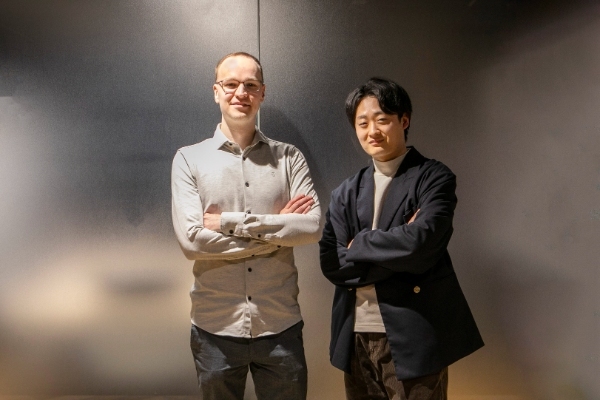近年ではAI技術の急速な進化により、AIを搭載したロボットによる高度な業務遂行が可能になっています。特に製造業や物流業、介護、接客などの分野では、AI搭載ロボットで業務効率化や人手不足の解消を実現する例が増えてきました。
さらに技術が進歩していくと、AI搭載ロボットはどのような業務で活躍するのでしょうか。本記事では、AI搭載ロボットの導入効果や将来性に加えて、現時点での活用事例を紹介します。
AI搭載ロボットとは?
AI搭載ロボットとは、従来のロボット技術にAI(人工知能)を搭載することで、自律的な作業を可能にしたシステムです。人の脳と同じように考える特性があり、具体的には以下のような機能を備えています。
<AI搭載ロボットが備えている主な機能>
・ロボット自らが情報収集をして、膨大なデータから学習する
・人の言葉を理解し、最適な行動を取る(自然言語の処理)
・画像や音声を複合的に認識する
2023年に開催された国際サミット「AI For Good」では、世界で初めてロボットと人間による記者会見が行われました。高度なコミュニケーションに加えて、精密な作業や監視、状況判断も可能になったことから、AI搭載ロボットは様々な業界で実用化が進められています。
Google発のスタートアップが基盤モデルを開発
AI搭載ロボットの将来を担う技術として、近年では「π0(パイゼロ)」と呼ばれる基盤モデルが注目されています。
様々なロボットに搭載できるπ0は、Google発のスタートアップ「Physical Intelligence社」が開発を進める基盤モデルです。テキストの処理や生成を行う大規模言語モデル(LLM)と、画像生成などに使われる拡散モデルの組み合わせにより、複雑なタスクを柔軟にこなすことが期待されています。
すでに行われた実証実験では、絡まった洗濯物を1枚ずつ畳んだり、テーブル上の皿とゴミを区別して片づけたりなど、状況に合わせて的確に判断できることがわかりました。このまま順調に開発が進めば、より高度なタスクをスムーズにこなす「π1」や「π2」が登場するものと予想されます。
参考:Physical Intelligence Our First Generalist Policy
日本政府もAI搭載ロボット開発を推進
内閣府は破壊的イノベーションの創出をムーンショット目標※を掲げ、「ムーンショット型研究開発制度」において、AI搭載ロボット開発を推進する方針を明らかにしています。目標のひとつに「2050年までに、AIとロボットの共進化により、自ら学習・行動し人と共生するロボットを実現」を掲げており、その実現に向けて次のターゲットが設定されました。
※ムーンショット目標:壮大で非常に困難が伴うが前人未到で可能性に満ちた計画のこと
<6つのターゲット>
1. 2050年までに、人が違和感を持たない、人と同等以上な身体能力をもち、人生に寄り添って一緒に成長するAIロボットを開発する。
2. 2030年までに、一定のルールの下で一緒に行動して90%以上の人が違和感を持たないAIロボットを開発する。
3. 2050年までに、自然科学の領域において、自ら思考・行動し、自動的に科学的原理・解法の発見を目指すAIロボットシステムを開発する。
4. 2030年までに、特定の問題に対して自動的に科学的原理・解法の発見を目指すAIロボットを開発する。
5. 2050年までに、人が活動することが難しい環境で、自律的に判断し、自ら活動し成長するAIロボットを開発する。
6. 2030年までに、特定の状況において人の監督の下で自律的に動作するAIロボットを開発する。
引用:内閣府 ムーンショット目標3 2050年までに、AIとロボットの共進化により、自ら学習・行動し人と共生するロボットを実現- 科学技術・イノベーション
すでに東京大学などの学術機関では、人との協働や融和を目指す研究開発プロジェクトが進められています。
AI搭載ロボットと通常のロボットの違い
通常のロボット(非AI搭載ロボット)がこなせる業務は、事前にプログラムしたタスクのみです。膨大なデータの解析や、状況に合わせて判断する機能は備わっていないため、運用期間に応じて進化することもありません。
以下の表は、AI搭載ロボットと従来型のロボットの違いをまとめたものです。
| 比較項目 | AI搭載型 | 従来型 |
|---|---|---|
| 環境認識・判断 | ・カメラ、センサーなどで複雑な環境を認識し、AIが状況を判断 ・自律的に行動する |
・センサーなどで環境の情報を取得する ・事前にプログラムされた処理を行う |
| インタラクション性 | ・自然言語処理による対話が可能なものもある | ・スイッチやレバーなどで事前に設定された操作ができる |
| 学習の仕方 | ・過去のデータや経験からAIが自律的に学習し、性能を向上させることができる | ・事前にプログラムされた動作を繰り返すのみで、自律的な学習能力はない |
| ルーチンに対する対応 | ・ルーチンワークをこなすだけでなく、効率をあげるよう自律的な改善を行う | ・事前にプログラムされた手順に従い、正確にルーチンワークを繰り返す |
| 未知の状況への対応 | ・過去の学習データに基づいて柔軟に状況を理解する ・適切な行動を生成しようとする |
・プログラムされていない状況には対応できない ・停止したり、誤った動作をする可能性がある |
自己学習機能が備わったAI搭載ロボットは、運用期間に応じて作業品質が向上します。
例えば、IoT機器との連携で作業データを収集できる仕組みにすると、膨大なデータに基づいてAI自身が状況に応じた判断や動作を自己学習します。運用期間に応じて対応できるタスクが増えるため、システムによっては多品種多変量のタスク(自動車の部品組み立てやECサイトの出荷処理など)をこなすことも可能です。
AI搭載ロボットの導入効果
現在のAI搭載ロボットは、データに基づいた業務の遂行や分析、異常検知などを得意分野にしています。実際の現場でどのように活躍するのか、ここからはAI搭載ロボットを導入した場合の主な効果を3つ解説します。
<AI搭載ロボットを導入した場合の主な効果>
1.人手不足を解消できる
2.複雑なタスクでも品質のばらつきを防げる
3.現場の安全性が向上する
1.人手不足を解消できる
通常のロボットとは違い、AI搭載ロボットは単純作業から複雑なタスクまでこなせます。属人的な作業を任すことができれば、これまでの担当者は別の業務に時間を割くことができます。
この流れが広範囲に広がると、社内全体の人的リソースを最適化できるため、結果としてAI搭載ロボットは人手不足の解消に貢献します。
2.複雑なタスクでも品質のばらつきを防げる
AIには自己学習の機能があるため、運用期間に応じて作業品質を均質化する効果も期待できます。
例えば、小さな部品を取り扱う製造現場では、状況に合わせて部品の位置を微調整したり、細かい部分まで検品したりする作業が必要です。このような現場でも、AI搭載ロボットは作業データをもとに自己学習をするため、作業を繰り返しながら判断や動作を最適化し、品質のばらつきを防げる可能性があります。
3.現場の安全性が向上する
AIの自己学習機能は、建設現場や生産現場の安全性を高めることにも寄与します。例として、従業員に危険物(車両や機器など)の接近を知らせるシステムについて考えてみましょう。
従来のロボットではレイアウトなどの現場状況が変わると、危険物を検知できなくなる可能性があります。一方、AI搭載ロボットは自己学習によって未知の状況にも対応しようとするため、初めて導入される現場や、既に導入されている現場のレイアウト変更にも、比較的時間をかけることなく危険物の検知を開始・継続できるというメリットがあります。
システムによっては、導入当初に想定していなかった危険物(部外者や落下物など)を検知できる可能性もあります。
AI搭載ロボットの活用事例5選
AI搭載ロボットは、すでにビジネスの場で幅広く活用されています。人に代わって作業をするだけではなく、複雑なタスクを高精度にこなすロボットも登場しました。以下では開発段階のものも含めて、実用化が進められているAI搭載ロボットの事例を紹介します。
<AI搭載ロボットの活用事例5選>
1. 運搬から検品までこなす人型ロボット/製造業
2. 自律走行でサポートが必要な作業員を発見/物流業
3. 収穫適期のピーマンを自動で収穫/農業
4. 施設内の除菌作業とパトロールをこなすロボット/介護
5. 模造皮膚の縫合手術/医療
1. 運搬から検品までこなす人型ロボット/製造業

出典:PRTIMES 大阪万博 中国館にて、ヒューマノイドロボットが来場者と交流 ─ UBTECH社製 二足歩行ロボット「Walker」
中国のUBTECH Robotics社が開発した『Walker Sシリーズ』は、世界的な自動車メーカーにも採用されている人型ロボットです。運搬や仕分け、検品作業などを代行するのに加えて、テキストや音声を使ったコミュニケーションも実現できます。
2024年からトレーニングを行っていた『Walker S1』は、ミリ単位での精密検査や、最大15kgのコンテナを搬送するなどの能力を備えています。パトロールや接客業務にも対応できるため、製造業以外での活用も期待されています。
参考:UBTECH Robotics WalkerS1-UBTECH
2. 自律走行でサポートが必要な作業員を発見/物流業

出典:PRTIMES 15th Rock、ロボティクス企業「Robust.AI」に出資。日本市場進出も支援
米国のスタートアップ「Robust.AI」は、倉庫内で働く作業員のボディーランゲージを察知し、動作や体勢から「何をしようとしているのか」を自律的に判断するAI搭載ロボットを開発しました。『Carter』と名付けられた本ロボットは台車のような形状をしており、倉庫内を移動しながら作業員をサポートします。
タッチスクリーンが備わったハンドルバーを作業員が握ると、『Carter』は瞬時に手動操作へと切り替えます。また、複数台のカメラを搭載することにより、近くの作業員が考えていることを解析する仕組みを実現しました。これらの機能を使い分けることで、『Carter』は倉庫内での効率的な作業をサポートしてくれます。
参考:WIRED.jp 人間の意図を“察知”するロボットが、倉庫で作業員たちと協働し始めた
3. 収穫適期のピーマンを自動で収穫/農業

出典:PRIMES AGRIST株式会社と株式会社マクニカ、宮崎県とピーマン収穫ロボットによる持続可能な農業の実現に向けた次世代農業事業における連携協定を締結
AGRIST株式会社が開発した『L』は、成長したピーマンを自動収穫するロボットです。AIを使った画像検出により、収穫適期のピーマンを高精度で判別できるシステムを構築しました。
本体に備わっている収穫ボックスが埋まると、『L』は自律的にコンテナへと移動し、ボックス内のピーマンを放出します。路面状況による影響を避けるために、畑の上部にはU字型レールを通し、畝間を吊り下げ式で移動する仕組みにしました。2024年4月には、キュウリ収穫ロボットの最新動画も公開されています。
参考:AGRIST株式会社|【製品紹介】吊り下げ式ピーマン自動収穫ロボット「L」
4. 施設内の除菌作業とパトロールをこなすロボット/介護

出典:PRTIMES AI搭載型ロボット「アイオロス・ロボット」の開発・販売を行うAeolus Robotics社、総額2,000万ドル(USD)の資金調達を実施
介護現場で活躍するAI搭載ロボットには、米国のAeolus Robotics社が開発した「Aeolus Robot(アイオロス・ロボット)」があります。
Aeolus Robotは人型のロボットで、目にあたる部分には3Dビジョンを搭載。足部分には障害物を避ける各種センサーが付いており、モノをつかむ2本のアームも備わっています。
Aeolus Robotは人物認識のほか、物体認識やスムーズな歩行、除菌作業などが可能です。夜間になると施設内を巡回し、住人が安心できるようにパトロールをしてくれます。
5. 模造皮膚の縫合手術/医療
カリフォルニア大学バークレー校の研究チームは、縫合手術をする外科ロボットを開発しています。実用化に向けては課題が残されていますが、2024年には模造皮膚を6針縫うことに成功しました。
ロボットアームで針を完全にコントロールすることや、皮膚のように変形する物体をモデル化することは、現在の技術では難しいとされています。それにも関わらず、本ロボットは2台のカメラで針の位置を識別し、縫合プロセスの一部をこなしました。
2024年2月時点では6針ですが、動物の皮膚を使った実験などを通して、将来的にはより速く正確な縫合プロセスを実現することが期待されています。
参考:MIT Technology Review AIロボットが縫合技術を習得、6針縫うことに成功
自社に導入できるAI搭載ロボットを探してみよう
AI搭載ロボットは、業務の効率化や人手不足の解消、安全性向上など、多くの効果をもたらす存在として注目されています。製造、物流、介護、農業、医療など幅広い分野で導入が進んでおり、選択肢も多様化しています。
自社への導入を検討する際には、抱えている課題や業務フローを見直し、最適な機能や規模を備えたロボットを選ぶことが重要です。また、導入後のサポート体制や拡張性もあわせて確認しておきましょう。
AI技術の進化は加速しているため、早めに情報収集を進め、時流を捉えた最適な一手を打つことが、今後の競争力強化につながります。未来を見据えた準備を、今から始めてみてはいかがでしょうか。
関連記事
・AIアシスタントとは? 仕組みやサービスの例と導入のメリットを解説
・動画解析AIの導入プロセスとは? 5つのステップと注意点、最新の活用例を解説
・AI技術を用いて医療・介護の課題解決 現場の想いを込めた『まもあい』が提供する価値
・感情認識AIとは? 人の感情を読み解く革新的技術の仕組みと未来展望