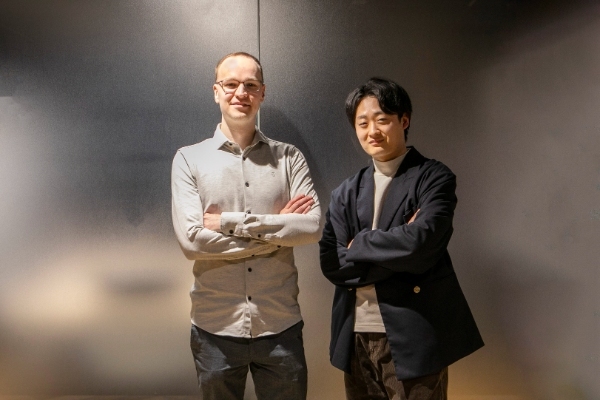エンジニアの素顔を紹介する「エンジニアのヨコガオ」。今回は、2022年入社の池内紀貴にフォーカス。“継続こそ力なり”を地でいく彼が、まさにいま直面している壁と、その先に見据える理想のエンジニア像とは?
2022年入社後、顔認証決済システムの保守・運用を皮切りに、顔認証解錠案件の設計や位置情報把握アプリの開発など多様な業務に携わり、その間、イノベーションチャレンジや社外のビジネスコンテストにも積極的に参加。現在は顔認証決済とブロックチェーンを利用したつながり可視化ツール「KOUKA」の連携開発に従事する。趣味は筋トレ。
書道で鍛えた「集中力」と「継続力」

――学生時代は主にどんなことを学ばれていましたか?
大学院まで進学し、ストレス計測と家電制御をテーマに研究していました。具体的には、ウェアラブルデバイスで取得した生体データからストレス状態を推定し、その度合いに応じて照明や空調などの家電を調整する、といったシステムの開発です。
――ストレスとテクノロジーを結びつけたきっかけは?
家族が心労で体調を崩したことがあり、ストレスが暮らしに与える影響には以前から関心を持っていました。もし、それを可視化できれば、早めに気づいて対処できることもあるのでは…そんな思いもあって研究に取り組むようになったのです。
また、学生時代には自営業をしている兄の仕事を手伝う機会もあり、Excelのマクロと外部のWeb APIを組み合わせて、業務に関連するデータを自動で取得・整理するツールを作成するなど、ちょっとした場面で技術の知識を活かすと、「え、そんなこともできるの⁉」と驚かれることもあって。自分のスキルが誰かの役に立つのが純粋にうれしかったし、楽しかった。その感覚は今の自分にもつながっていると思います。
――就職先としてCACを選んだ決め手は?
大学院で研究を進めるなかで、『リズミル』というCACのプロダクトを知ったのが最初の接点です。スマホをはじめとした身近なデバイスを使って、心拍数などのバイタルデータを非接触でセンシングするというもので、当時はとても先進的だと感じました。
入社の決め手になったのは、独立系のSIerとして、上流工程から携われる元受け案件が多いこと。そして、社員の勤続年数が業界内でも長く、じっくりと腰を据えて成長できる環境があることです。自分自身、コツコツと継続することが得意なので、その点に自分との相性の良さを感じました。
――これまでに継続して取り組んできたことがあれば、教えてください。
たとえば書道は、小学1年から大学3年まで10年以上続けました。5段の資格も取得しています。書道の魅力は、目の前の一文字に集中できること。少しでも気が散ると、すぐに字に表れてしまいます。書道を長年続けるなかで、自然と集中力が養われたように思います。
開発とマネジメント、その両立から見えてきたもの

――インテグレーションP&S部では、どのような役割を担っていますか?
インテグレーションP&S部は、既存のプロダクトや技術を組み合わせ、新しい自社サービスを生み出す部門です。部署内でアイデアを立ち上げることもあれば、当社の新規事業開発本部の企画をプロダクトとして形にする役割も担っています。
私はこれまで、クラウドからアプリケーションまで分野に偏らず幅広い技術に触れてきました。現在は、AWSを用いたクラウド構築や、Webアプリケーションの開発に携わっており、フロントエンドからバックエンドまで一通り対応ができることが強みです。
技術的な引出しが多いと、「この課題はインフラで解決できそう」「いや、業務フローの見直しが先かもしれない」といった具合に、さまざまなアプローチができる。そうした俯瞰的な視点を、これからも深めていきたいと考えています。
――現在、どのようなプロジェクトに取り組んでいますか?
いま進めているのは、CACのプロダクトである「KOUKA」と「顔認証決済システム」を組み合わせた新サービスの開発です。「KOUKA」は、社員同士の感謝や称賛をトークンとして送り合い、人や組織の状況を可視化できるツール。今回はトークンを送り合うことで発生する報酬ポイントを使って、顔認証で商品購入ができるようにしようという試みです。
――ふたつのシステムの連携に着目したきっかけは?
はじまりは、コンビニエンスストアがレンタル提供しているセルフレジ端末に関する取り組みでした。「この端末を使って、何か新しいサービスをつくれないか」、そんなテーマが社内で持ち上がったのです。
このレジ端末には、私も開発に関わった顔認証決済システムが組み込まれていて、それと何かを掛け合わせれば、新しい価値を生み出せるかもしれない。そこから模索が始まりました。いくつもアイデアを出しては「ちょっと違うかも…」とやり直す日々。試行錯誤を重ねた末、「KOUKA」との組み合わせなら「形にできそうだ」と、突破口が見えた気がしました。

――新しいプロダクトを企画する難しさもあったのでは?
企画段階から関わるのは、今回が初めての経験でした。「自分が欲しいサービスとは何か?」「誰が、どこで、何に困っているか?」といった抽象的な要素があるなかで、何から具体化するかを一つひとつ形にしていく作業は本当に難しかったです。
明快な道筋があったわけではありませんが、思いついたアイデアを何度も検証していくなかで、「使う人のことを第一に考える」という視点を持てるようになりました。
上長に『KOUKA×顔認証決済』のコンセプトを提案し、「それ、しっくりくるね」と言われたときは素直にうれしかったです。何度も軌道修正を繰り返してきただけに、「これでやっと前に進める」と手ごたえを感じた瞬間でもありました。
――プロジェクトはその後、どのように進んでいますか?
2025年3月から、「KOUKA」と顔認証決済システムの連携開発が始まりました。私はエンジニアとして顔認証側の開発を担いつつ、「KOUKA」側の開発を一部のメンバーに任せ、全体を統括する役割も担っています。
開発とマネジメントの両立はCACでは珍しくないものの、実際にやってみると想像以上に大変です。特に最近感じているのが「説明力」の大切さ。ただ、「このタスクをお願い」と指示するだけでは、その範囲しか見えなくなってしまう。だからこそ、「このシステムで何を実現したいのか」というゴールから伝え、「だから今、この開発が必要なんだ」と背景を含めてタスクを振るように心がけています。
目的が見えると、タスクは単なる作業ではなく、自分ごととして捉えられるようになります。そのための働きかけは、マネジメントではとても重要だと学びました。
――進行中のプロジェクトで苦労している点があれば教えてください。
特に社内調整には苦労しています。現在は、顔認証で「KOUKA」のポイントを使える仕組みを、福利厚生として導入できないか検討しているのですが、実現するには総務部や経理部との連携が欠かせません。「社内制度にどう組み込むか」「会計処理はどうなるか」といった細かな点を、担当部署とすり合わせながら仕様に落とし込んでいく必要があります。
開発と並行して社内調整を進めるのは負荷も大きいですが、その分、「どうすれば意図が伝わり、納得してもらえるか」といった提案力や交渉力が磨かれている実感もあります。
筋トレを活力に、ITアーキテクトの道を歩む

――システムをつくるだけではなく、それをビジネスにどう活かすか。その視点は、どこで培われたのでしょう?
入社1年目の後半に、JISA(一般社団法人 情報サービス産業協会)が主催する「ITアーキテクト寺子屋」という育成プログラムに参加したのが転機でした。5日間のワークショップを通じて、初めて「ITアーキテクト」という役割について学んだのです。
システムを設計するだけでなく、技術とビジネスの両面を見据えて最適解を導く。そんな役割に惹かれて、「自分もこうなりたい」と思うようになりました。それ以来、アーキテクト的な視点が求められる場面には、自分から積極的に関わるようにしてきました。
――とはいえ、ビジネス要件とシステム要件を両立させるのは簡単ではないですよね。
そうですね。私自身、ビジネス要件に直接関わった経験は多くありませんが、学んでいくなかで難しさを感じるのは“非機能要件”の部分です。たとえば、セキュリティ対策や「24時間365日止まらずに動くこと」といった、システムの裏側を支える要件です。
一見、「それって当たり前だよね」と思われがちですが、万が一のシステム障害に備えてすぐに復旧できる仕組みを整えるには、それなりのコストがかかる。費用対効果を踏まえて、そうしたコストの必要性をどう説明し、納得してもらうか。まだ想像の域ではありますが、実際に調整していくのは難しいだろうなと感じています。
――そこがITアーキテクトをめざすうえで、乗り越えるべき壁だと。
そう思います。技術だけでは不十分で、今後はますます「説明する力」が問われてくるかと。「なぜそれが必要なのか」を、誰にでもわかる言葉で、いかに論理的に伝えられるか。その力をもっと磨いていかなければと感じています。
――将来的には、どんなエンジニアになりたいですか?
技術的な議論が行き詰まったとき、その人が加わると場の空気が変わる。何を聞いても的確な答えが返り、相談すれば必ずヒントがもらえる――社内に、そんな先輩がいるんです。いつか自分も、そうなりたいと思います。
目指しているのは、幅広い技術を自在に組み合わせて、最適なアプローチを導き出せる存在。社内外から信頼される一人前のITアーキテクトとして、しっかり自分の軸を持てるようになりたいと思っています。
――ちなみに、シャツ越しにも分かるその体格。筋トレがご趣味なんですか?
はい、学生時代から続けています。最初のきっかけは、「細マッチョになってモテたい!」という単純な動機でした(笑)。でも続けるうちに、やった分だけ身体に成果が表れていく感覚にハマってしまって。
筋トレって、コツコツと積み重ねればちゃんと結果がついてくる。その実感が、ほかでは得られない自己肯定感につながっている気がします。だから、仕事で壁にぶつかっても、それほど落ち込まずに済む。今では週3~4回のジム通いが活力源になっています。

一見すると穏やかな雰囲気の池内さんですが、書道で培った集中力や、筋トレを継続する粘り強さからは、静かな意志の強さが感じられます。新しい領域にも臆せず挑み、開発とマネジメントの両輪を力強く回す姿には、未来のITアーキテクトとしての片鱗が垣間見えました。
▽技術者が気になる技術
最近注目しているのは「Web3.0」です。これまで企業という枠のなかで、中央集権的に管理されていた個人のスキルや実績が、「Web3.0」が実現する分散型の仕組みによって社外でも証明できるようになるかもしれない。そんな可能性に惹かれています。
たとえば、私が開発に関わっている「KOUKA」では、社員同士の感謝のやりとりをスコア化し、ランキングとして可視化されます。たとえ「感謝された回数 12カ月連続トップ」という実績があっても、これまで社内だけに埋もれていました。もしそれが、個人の実績として証明可能なかたちで外に持ち出せるようになれば、キャリアや評価の仕組みそのものが変わっていくはず。そうした世界観を技術的に可能にするのが、Web3.0なのだと感じています。