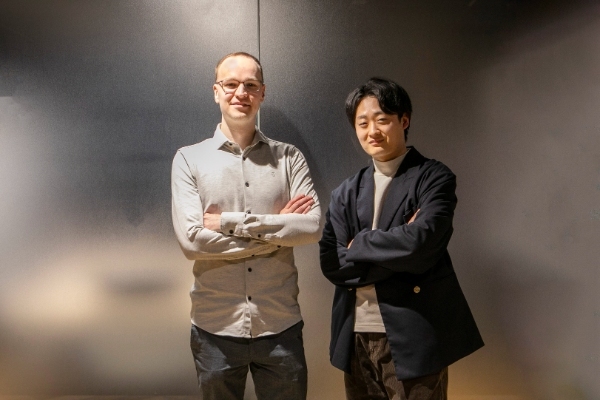株式会社シーエーシー(以下、CAC)は独立系SIer企業だ。受託事業を主な収益の柱としてきたが、中期経営計画「CAC Vision 2030」の中で、新規事業開発をもう1つの柱として定めた。
すでに新規事業としていくつかのサービスがローンチされているが、その多くのプロダクトの背景には、R&D(研究開発)本部による技術開発がある。設立当初からトップを務める鈴木貴博に、これまでの取り組みや成果、今後への展望を聞いた。
2002年、株式会社シーエーシー入社。生産品質強化本部副本部長兼生産技術部長、技術企画本部長などを歴任。2022年R&Dセンター長を経て、2023年にR&D本部長に就任。
――まずは経歴を教えてください。
鈴木 もともと流通系の会社にいて、業務の効率化を担当していました。当時はまだPCが登場し始めた頃で、そこからIT系の仕事をしたいと思い、CACに転職して20年以上が経ちました。CACに入社した理由は、システムを構築する数多くの会社の中で、作ることにこだわりがある会社に見えたからです。CACでは開発案件でマネジャーなどを担当しつつ、徐々に技術全般を見る役割になっていきました。現在はCACの取締役、CTO、R&D本部のトップを務めています。
――R&D本部が立ち上がった経緯を教えてください。
鈴木 以前から技術ベースで事業展開をしようと、独自のプロダクトを作ることは試みていましたが、新たにR&D本部と新規事業開発本部ができ、そこでR&Dと事業開発の機能を明確化しました。もともと企画やマーケティングをやっていた人たちは新規事業開発本部に、技術中心の人たちはR&D本部に、という流れです。既存の受託事業をやっていた一部の人にもR&D本部に入ってもらい、新規事業も既存の受託事業も担えるような組織となっています。
R&Dでは技術の研究だけでなく、技術を価値に変えるために何かのアプリケーションにしていくことを大事にしています。AIが主軸でありつつも、AIだけでシステムが動くわけではないので、周辺技術の研究開発も行っています。
――AIは特に変化のスピードが速い領域ですが、どのように研究を進めているのでしょうか。
鈴木 領域が広いので、我々の強みを考慮して、バランスを見ながら情報を追うようにしています。今のAIは想像以上に進化しているので、「この領域ならいけるのではないか」と勝負する場所を選ぶのが年々難しくなっていると感じています。AIの可能性が広がったり、逆に閉じて見えたりするようなときがあり、状況に応じて、CACで勝負できる領域を見据えるように意識しています。

――R&D本部はどういったメンバーで構成されているのでしょうか。
鈴木 若手が多いですね。30人近くいて、そのうちの3分の2は新卒で入って5年目くらいまでのメンバーです。AIの分野はこれまでの技術とは違うので、学習という点ではキャリアがある人が新しく覚えるのと、キャリアの浅い人が覚えるのはあまり変わらないんです。プログラミングや実装に慣れ親しんできた若手も入ってきています。ある程度こちらからフォローしますが、基本的には自発的に動いてくれるメンバーばかりです。
――最新情報のキャッチアップはメンバーにも奨励しているのでしょうか。
鈴木 特別にこちらから仕掛けを作っているわけではないのですが、積極的に情報を取り入れるメンバーが集まっています。そういう人が情報を共有していくと、他の人も触発されて勉強し、発信をするようになることもあります。チーム内で自発的に情報共有をする雰囲気ができていますね。
――そうなるとチームが求める人材は技術が好きなタイプになるのでしょうか。
鈴木 そうですね。技術が好きで、追求できる人がいいと思います。自らの時間を費やして技術を学習することが、後々のアウトプットにつながります。好きで時間を忘れてやってしまうタイプの人じゃないと、なかなか成功するのが難しい領域に我々はいます。逆にそういう人にとっては、力を発揮しやすい環境が整っていますね。好きで突き詰めたい人が来てくれると、我々にとっても本人にとってもいいのではないかと思います。
――R&D本部起点の企画で、印象に残っている事例はありますか。
鈴木 AIによる画像認識を使って面接対策を手助けする『カチメン!』や、介護現場向けの転倒検知のプロダクト『mamoAI(まもあい)』は手応えを感じました。もともとこちらで取り組んでいたAI技術が、新規事業開発本部のビジネス視点も加えて、プロダクトとして立ち上がったものです。まだ日は浅いですが、拡大できるビジョンが見えているのは大きいです。我々だけだとこのレベルには達することが難しかったので、いいコラボレーションができたと感じます。我々としても培ってきた技術が実際にプロダクトになったことで、自信を深めることができました。
――新規事業開発本部とのタッグが大きかったのですね。
鈴木 『カチメン!』はもともとプレゼン練習のプロダクトから始まっています。R&D本部でも「面接対策に使えるんじゃないか」と話題に挙がりましたが、アイデアが出ただけでした。その後、新規事業開発本部とのコラボレーションが始まり、最初に彼らから出てきたアイデアも同じ面接対策でした。ある意味我々がやりたくても手が出せなかったプロダクトを、彼らが形にしてくれたという流れです。共創によってプロダクトになったことが印象に残っています。
――一方で、プロダクト開発にあたってAI技術ならではの難しさはありましたか。
鈴木 一番は精度ですね。ほぼ間違いなく、といえる精度まではいきますが、どこまでやっても100パーセントにはならないんです。なかなか精度が上がらないという壁にぶつかることはよくあります。コンペではいい成績が出ても、実務に活かそうとする段階で、その精度では厳しいと判断されることもありました。

ただ、この分野でおもしろいのは、論文も含めて短期間でたくさんの情報が出てくることです。論文を参照しながら試したり、あるいは全く違うことを思いついて試したり、泥臭い作業を繰り返して学習データを増やしたりと、いろいろなことを試しながら精度を上げられるようにしています。
――R&D本部は長崎県に拠点を置いて、AIの普及などに取り組んでいます。この活動はどういった経緯でスタートしたのでしょうか。
鈴木 ITの価値を届けられる可能性がある地域に拠点を作っていこうという話が社内で出たのがきっかけです。R&D本部として様々な知見や技術が蓄積されていたので、そうした技術を提供できるようなラボを開設しました。これまで関わっていなかったようなお客さまや分野にもリーチできるようになりました。

ラボを開設することになったきっかけは、見せないとわからないものって多いなと思ったからです。AIはこんなふうに使えるんだよと、見せられる場所を用意しました。実際に地元の人がラボに来てくれることも多く、それぞれの業種に合わせてAIの使い方を一緒に考えるようなこともあります。他にも東京の企業が長崎に来て、実際に技術に触れて、東京に戻って共創が始まるケースもありました。
――地元の産業とはどういった取り組みが生まれていますか。
鈴木 地域に根ざしたアプローチをしています。例えば魚の養殖現場における魚体の画像認識などがその1つです。魚が何匹いて、どう育つのかを、AIの技術を使って可視化できるようなプロダクトです。
他には教育の現場にも関わっています。若い人の流出が地方で問題になっていますが、ITは他の業種に比べて、場所を選ばない働き方がしやすいです。そういう分野に携わりたい人を増やしていくためにも、大学にAIを提供して研究に活かしてもらったり、授業のお手伝いをしたりと、ITへのタッチポイントを増やせるような取り組みをしています。先ほど挙げた『カチメン!』は長崎の学校にトライアルとして提供もしています。
――CACのR&D本部ならではの強みはどこにあると思いますか。
鈴木 研究もそうですけど、実践を重視する会社ということは挙げられます。ただ研究しました、ではなく、アプリケーションとして提供できるところまでやって実践です。またR&D本部とは別に新規事業開発本部という、技術をビジネスにしてくれるチームがあって、そこに投資している点もCACならではの強みです。
――ここまでの取り組みの手応えはいかがでしょうか。
鈴木 今話題のChatGPTは汎用的なものですが、より特化したものが業務や社会課題の解決に使われるようになってくるでしょう。その流れの中で、我々はAIのサービスを作れるR&D本部と、事業化できる新規事業開発本部があります。会社として、AI技術と新規事業開発どちらも武器になっているという手応えがあります。
――今後、どういった領域でAI技術を活かせると考えていますか。
鈴木 領域は絞れるものではないかもしれません。これまでのITとは違って、今までできなかったことができるようになる、今はその過程にいます。我々のビジネスも大きく様変わりするでしょう。
CACは今まで金融分野や製薬分野が主な開発領域でしたが、今ではAI技術を活かして漁業や農業、製造業にも領域が広がってきました。ITが届かなかったところにITの価値を届けられるようになり、今後ますます広がっていくだろうという感覚はあります。ビジネス的な部分は新規事業開発本部の力を借りつつ、我々は必要な技術を研究して蓄積していきたいですね。
――R&D本部としての今後の展望を聞かせてください。
鈴木 現状に手応えを感じています。R&D本部が今の形になってまだ数年ですが、力を入れていけばさらに結果が出るんじゃないかと期待しています。新規事業でもそうですが、既存事業でもR&Dの力を活かしていければ、両輪で良くなっていくと思います。新規事業のためのR&Dと既存事業のためのR&D、どちらに偏りすぎてもだめなので、その舵取りをうまくやれるかが今後のカギになると考えています。
関連記事