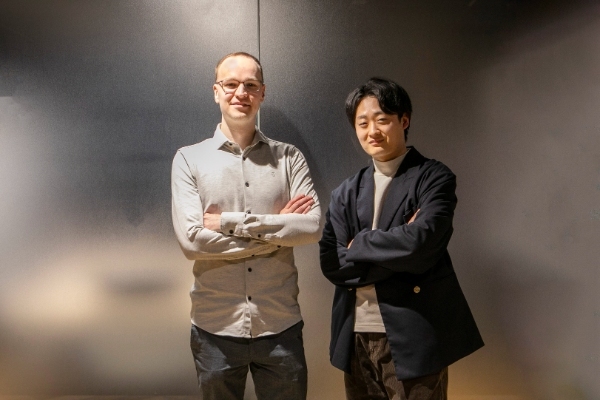1998年早稲田大学人間科学部卒業後、医療サービス会社に勤務。2001年からアメリカに留学し、2005年にCAC Americaに入社。 2012年に日本に帰国しCACへ、複数の新規サービスのマーケティングや運営、プロダクトグロースなどを担当。2022年4月より感情認識AI『Affdex』のセールスを担当、感情センシング技術の展開を推進している。2024年1月からはプロダクトオーナーを務める。
こんなお悩み、ありませんか?
コミュニケーション研修や接客トレーニングを担当されているみなさん、こんなお悩み、ありませんか?
- OJTで「もっと笑顔で!」と指導しているが、効果がいまひとつ
- ロールプレイでの評価が属人的で、受講者が改善ポイントを掴みにくい
- 第一印象や表情の良し悪しを言語化・数値化できずに困っている
- 現場任せの接客研修に再現性や体系性を持たせたい
こうした悩みは、接客・営業・受付など「人と接する業務」の現場で多く聞かれる声です。「印象が大事」と分かっていても、何をどう改善すれば良いか分からず、結局“センス”や“経験”に頼りがちになっていませんか?
従来の接客研修や新人教育は、言葉づかいやマナー、商品知識といった言語的なスキルに重点が置かれてきました。しかし、実際の現場で大きな差を生むのは、「その人がどう見えるか」「感じがよいかどうか」といった非言語的な印象ということも多いようです。
本記事では、こうした課題に対し、「印象力」や「笑顔」などの非言語スキルを表情データとして可視化し、反復可能なトレーニングとして改善を仕組み化するアプローチをご紹介します。心理学や行動科学に基づく知見も加えながら、企業研修の現場における“印象教育の再構築”を考察します。
印象力とは?──“見た目の印象”の影響力
「印象力」は抽象的に捉えられがちですが、心理学・コミュニケーション学の領域では以下のような要素に分けた分析がされています。
- 表情(例:笑顔、真剣さ、親しみやすさ)
- 声・話し方(例:トーン、スピード、明瞭さ)
- 態度・所作(例:姿勢、アイコンタクト、所作の丁寧さ)
- 言葉(例:話される内容、言葉遣い)
このうち「表情」は、相手に瞬時に伝わる、最も影響力の大きい非言語情報であることが、アルバート・メラビアンの研究* で明らかになっています。
初対面の瞬間に相手へ与える印象の多くは、言葉ではなく“見た目”に依存しています。実際に、ある人を「感じがいい」「親しみやすい」と感じるかどうかは、笑顔や視線、口角の上がり方、表情の柔らかさなど、ごく短い時間に視覚的に受け取られた要素によって判断されます。2005年に発売された『人は見た目が9割』** というタイトルの本が注目を集めたのも、こういった研究が背景にあるからでしょう。
だからこそ、印象力のトレーニングには“表情”へのアプローチが重要なのです。
** 『人は見た目が9割』竹内一郎,2005年, 新潮社
この本では「見た目」を表情だけでなく声、しぐさ、視線、姿勢、距離、匂いなど「非言語コミュニケーション」全体を指す意味で使っている。この「非言語コミュニケーション」こそが、相手に与える印象の大部分を形成する要素であると、著者は主張している
印象力は、心理学でも裏付けられている
印象の重要性は、心理学的にも明らかになっています。
▶ メラビアンの法則
上で述べたアルバート・メラビアンの研究は「メラビアンの法則」として知られています。人が他人の第一印象を判断する際、影響の割合は:
- 視覚情報(表情・見た目):55%
- 聴覚情報(声・話し方):38%
- 言語情報(話の内容):7%
つまり、「何を言うか」よりも「どんな表情・トーンで伝えるか」の方が印象に与える影響は圧倒的に大きいのです。
▶ 初頭効果
初頭効果とは、人が最初に得た情報を強く記憶し、その後の判断や評価に大きく影響を与える心理現象です。印象形成や学習で重要になります。人と会う場合を考えると、 第一印象がその後の評価に強く影響するということになります。
▶ 感情伝染
感情伝染とは、人の表情や声の調子、態度などを通じて感情が他者に移り、集団内で広がっていく現象を言います。無意識に起こることが多いとされています。人と対面している場合、相手の表情、声、態度が自分の感情にも影響を与えるということになります。
▶ 表情フィードバック仮説
表情フィードバック仮説によれば、笑顔を作ると楽しい気分になり、しかめ面をすると不快な気分になります。自分の表情が脳にフィードバックされ、その感情体験を強めたり変化させたりするという心理学の仮説を言います。
これらの研究に共通しているのは、「表情は単なる見た目ではなく、心と行動に影響を与える手段である」という点です。手段であれば工夫できる、つまり、印象力は“感覚”ではなく、“働きかけ・行動”によって高められるスキルなのです。
なぜ「もっと笑顔で!」が伝わらないのか
「もっと笑顔で」「感じよく話して」── 接客研修や新人研修でよく使われる指導フレーズです。しかし、このような抽象的な言葉が、必ずしも相手に伝わるとは限りません。
誤解されやすい抽象的指導
- 本人は「笑っているつもり」でも、相手にはそう見えていない
- 作り笑いになり、かえって不自然な印象になる
- 指導者によって表情評価の基準がバラバラで、混乱を招く
新人ほど困惑しやすい
- 「印象が大事」と言われても、何を直せば良いか分からない
- 指摘されても改善できず、自信を失う
- 「結局センスだ」と思い込み、あきらめてしまう
こうした背景から、“印象力”の育成は属人化・形骸化しやすいのです。評価方法も改善方法も曖昧で、研修担当者側も効果測定ができない状況が続いているのではないでしょうか。
表情や印象は、「センス」ではなく「スキル」
表情は、顔の筋肉の動きによって構成されています。つまり、再現可能な“運動”です。“運動”だからこそ、トレーニングとフィードバックのサイクルによって改善・強化できます。
これは、スポーツや楽器の練習と同じ。「なんとなくの感覚」ではなく、
- どの筋肉が足りないのか
- どう動かせば良いのか
を自覚し、反復して練習できる環境が必要です。
さらに重要なのは、本人が「できているつもり」と「実際の見え方」とのギャップに気づくこと。これは自己認知だけでは限界があるため、客観的なフィードバックが欠かせません。
PCやスマホで印象力を鍛える
これまで表情のスキルを磨く手段といえば、鏡を見て練習する、人に指摘してもらう、ビデオで撮って見直すといった方法が中心でした。しかし、表情分析の理論が体系化されたFACS(Facial Action Coding System)の普及や、PCやスマホで動画を簡単に撮影できる環境の整備により、新たな選択肢が生まれています。現在は、PCやスマホで撮影した映像をアプリで解析し、評価するツールが数多く登場しています。
CAC identityが提供する「心sensor for Training」もその一つ、印象力を“見える化”し、訓練することができる表情トレーニングアプリです。
▶ 「心sensor for Training」の主な機能
- 「笑顔」「真剣」「お詫び」「好感度」などシーン別の表情トレーニングができる
- カメラに向かって話すと、AIが自動で表情を解析・採点してくれる
- 動画の振り返りと数値フィードバックで自分だけでもトレーニングができる研修担当者は手軽にトレーニングコンテンツを作成することができる
▶ 「心sensor for Training」のトレーニングの流れ
「心sensor for Training」の典型的な使い方は次のような流れになります。
- 採点モードに挑戦する(例えば面接本番を想定してみる)
- 自動採点されるので、表情データの数値やパートごとのアドバイスを確認する
- 練習モードで苦手ポイントを集中練習する
- 再挑戦してスコア向上・変化を実感する
動画でこの流れを説明しているのでご覧ください。
▶ 「心sensor for Training」の習慣化の工夫
- スコアの成長が、繰り返しトレーニングすることのモチベーションに直結します
- 自分の表情を自分で見て気づける「動画フィードバック」を提供しています
- スキマ時間に一人で気軽に反復練習できます。練習しているところを他の人に見られる恥ずかしさがないのも、続けられる理由です。
お客様の現場からの声:「伝わる笑顔」が再現できるように
実際に心sensor for Trainingを導入いただいた企業からは、次のような声が届いています:
- ロールプレイ前の基礎づくりとして有効。事前に印象スキルの底上げができるため、現場OJTがスムーズになった。(生命保険会社、営業研修で利用)
- 笑顔が苦手だった新入社員が、数日間の練習で見違えるようになった。笑顔を作るのが楽しいと言っていた。(小売業、新人研修で利用)
- 指導の根拠が明確になり、納得感のあるフィードバックができる。これまで「感じが良くない」という指摘に困っていた。(サービス業、OJTで利用)
- 自分で動画とスコアを見て納得しながら改善できたことで、現場に出てからも堂々と対応できている。(接客業、OJTで利用)
- AI相手なので、何度も練習できてストレスフリー。(小売業、自主トレーニングで利用)
- 自分の表情だけでなく、相手の表情にも気付けるようになった。表情を見る力も育てられる。(人材派遣会社、自主トレーニングで利用)
これからのビジネスを左右する「スキル」としての“印象力”
これまで感覚や経験に頼っていた「印象指導」を、データに基づいた仕組みへと進化させることで、現場の負担を減らしつつ、研修効果の再現性を高めることができます。これは、社員一人ひとりのパフォーマンス向上だけでなく、顧客満足度の向上、ひいては企業のブランド価値を高めることにも直結します。
印象力を磨き、組織全体の「顔」となる社員を育成することは、これからのビジネスを勝ち抜くための「投資」として捉える必要があるのではないでしょうか。
▶ 今すぐ資料をダウンロード(無料)
👉 [資料をダウンロードする]
▶ オンラインデモ受付中
👉 [デモを申し込む]